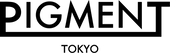マコトフジムラさんは、アメリカ在住の日本画材を使う現代美術家です。
また、アーティストとしての活動だけに止まらず、9.11の生存者であるご自身の経験から、被害者へ向けた社会活動にも従事し、その功績からブッシュ政権の元でホワイトハウスの文化顧問を担当しました。
今回PIGMENT TOKYOは、同氏のニュージャージー州にあるスタジオを訪ね、アートを志すまでのお話、アメリカで日本画の材料を使って作品を制作するということ、そして素材観から生まれる美学についてお伺いしました。
ー研究科生として日本にいらしたとお聞きしましたが、どのような経緯で日本にいらしたのでしょうか。
マコトフジムラ氏(以下、フジムラ/敬称略):大学時代はバックネル大学っていう大学行ってたんです。
そこはアメリカでいうリベラルアーツの学校だったんだけれども。
ペンシルベニア州ユニオン郡にあるのですが、その馬小屋を学生用のアトリエにした「アート・バーン」で絵を描いていていました。
その当時は油絵具だとかアメリカにある材料を使ってたんだけども、当時からずーっと水系絵具の方が自分の手にあうなと思っていて。
で、僕の先生はアメリカのカラーリストを代表するような水彩アーティストだったんです。

インタビューに答えるマコトフジムラ氏
ーどんな方だったんですか?
フジムラ:ニール・アンダーソンというアーティストです。
彼は水彩アーティストの中ではすごい知られている人なのですが、日本にすごく憧れていていたようで。
彼が「日本に戻ったことあるのか?」と私に質問したんです。「13才の時に帰って以降はないです。」と答えたら、「帰らないとダメだよ。」と言われまして。
僕はボストン生まれで、アメリカ国籍を持っているアメリカ人なのですが、小学校時代に鎌倉の学校に通っていたので、美意識っていうのはそこから流れているんじゃないかな。
その後、東京藝術大学に留学生として入学した時、齋藤典彦先生をはじめとして、稗田一穂先生、そして加山又造先生など、色々な先生にお世話になりました。
また当時は英会話教室をやってまして、そこには岡村桂三郎さん、千住博さん、村上隆さんが来てくれました。
ーまさに平成日本画の黄金期ですね。
フジムラ:大学院の博士過程の時は村上裕二さんが同じアトリエで。村上隆さんとも、いつも討論していました。
現代美術をはじめとして、「日本画とは何か?」という議題を軸に、今でも色々な(議論や作品が)展開がされているでしょう。ずっと日本で過ごした学生って、日本画のことを色眼鏡で見るじゃないですか。
僕は客観的に、日本画の材料そのものが素晴らしいんじゃないかと思ってるんです。

スタジオ周辺の様子。国立公園に隣接しており、自然溢れる環境で作品制作を行っている。
ー先ほどおっしゃっていた、鎌倉時代の経験というのは今の作品には影響がありますか?
フジムラ:すごく大きいと思います。母が亡くなった時、《Sea Beyond》 っていう胡粉だけを使った大作をカルフォルニアで描いていたんです。

《Sea Beyond》マコトフジムラ
2020年
サイズ(cm)335.28x213.36
ベルギー産リネン、膠、胡粉
これを描いていた時に、ちょうどカルフォルニアのニューポートビーチというところに居たんです。娘がその近くに住んでおり訪ねていったら、そこで母が亡くなったことを知りました。
そして朝早く海岸に行って、いろんなことを考えていたんだけど。水平線をずーっと見て、この先ってどこなんだろうと思って調べたら、そこが鎌倉だったんです。
ー運命的ですね。
フジムラ:その時に思ったのは、まずそういう絵を描くっていうことそのものを母が、こう、なんていうのかな、大切にしてくれた。僕が芸術家だとか、そういう新しいものを作るような仕事に就くことを、彼女はずーっと前からわかっていたようで。
鎌倉時代、夏は海岸で毎日遊んでいたから、それがすごく自分の美意識の底にあって。彼女が亡くなることを感性で捉えていたんじゃないかなと。
この作品は西洋の「Altar Piece」と言って三連画でひとつ真ん中のをあげるっていう、形式を採用した作品です。
この水平線の先に見える、視野を超えてその先に「見える」ものが何なのか、それがアートに与えられた大きな問いなのかな。
でもその先にあったのが、子供の時に体験した鎌倉の夏だった。僕の場合はそれが日本画に繋がっているし、こうしてカルフォルニアに繋がっていたんです。
ー制作することとキリスト教は密接な関係があるのでしょうか。
フジムラ:それはね、面白いことに、日本に戻って藝大へ留学してたきにクリスチャンになったんです。
ー生まれた時からクリスチャンだったのではないのですね。
フジムラ:「なぜわざわざ日本にきてクリスチャンになったのだろう?」ってずーっと思っていたんです。そして母が亡くなった後、記憶を辿っていくと、母の先祖に隠れキリシタンがたくさんいたんです。
僕の母方の祖父と祖母は教会の指導者だったと聞いていたんだけども、コネクションを作らなかった。だから僕は日本に帰ってからでないと、クリスチャンになれなかった。
日本に行くこと、それがひとつのCallingだったんです。
ーこれもまた運命的なエピソードですね。
フジムラ:藝大の修士課程時代は二子玉川に住んでいまして、そこには《Sea Beyond》と似た水平の橋がかかっており、修了制作ではそれをモチーフに描きました。
その橋は僕にとって、信仰というものがみえてきた橋なんです。

制作で使用されている群青の岩絵具
ーそこから、動画でも語られていたネオスとカイノスの話とも繋がるのですね。
https://www.youtube.com/watch?v=DEY22ixwfAQ
フジムラ:聖書には、新しいものを意味するギリシャ語がいくつかあって、それがネオスとカイノスという言葉です。
ネオスはまさにネオン。それは新しいiPhoneの様な新しさ。その年に新しいiPhoneがリリースされ、その次の年には古いものになる。それがネオス。
カイノスっていうのは新しい新しさ。全く新たなコンセプトの新しさ-キリストの復活はそうだと弟子のパウロは言っています。iPhoneの新しさではなくて、新しい新しさ。だから New Creation。
復活したイエスには傷跡があるでしょ。僕はあの傷跡っていうのは、すごく大切だと思っているんです。なぜスーパーマンじゃなくて人間なのか?それも人間だけじゃなくて、傷つけられた人間として復活したのか。
それは金継ぎにすごく近いな。新しい新しさっていうのは、金継ぎっていうのは直して使うためだけじゃなくて、新しものを作っている。
ー新しくお皿を買ってくるわけでも、アロンアロファでくっつけるわけでもなく。
フジムラ:それをわざわざ金で新しい線を引き、時に韓国の陶器と日本の陶器を継いでみたりもする。平和運動みたいな思想をもとに。日本だけじゃなく、韓国もそうだし、東洋の独特な何かがそこにあるんだなと思って。

ーそのカイノスっていう概念そのものが作品制作の中の哲学のひとつ?
フジムラ:そうですよ。それはずーっと考えていて。特に9.11のあと。
グラウンドゼロを目の前にして何を考えるかっていうと、まず最初にそこの痛々しい犠牲者を敬うことですよね。
その後、何もない荒地が美しく見えたんです。日が出てくる角度によって生じる屈折した美に、日本画そのものを感じました。
建物が倒れているところに光が当たると、そこにわーって何か新しいものが浮かぶんです。
ー本当は綺麗だと感じてはいけないはずなのに。
フジムラ:ただ、私は被害者でもあるわけだから、それをただ表現するっていうのは難しい。だから絵を通して、癒しを求めるんだと思います。
これが自分の先の人生に繋がらなかったらトラウマになって、それがそのままのアイデンティティーになっちゃいますよね。だからサバイバーっていうのは、複雑な必然性があって。
ー復興後、グラウンドゼロが元のビルに戻るのではなく。
フジムラ:君自身もそうでしょ。自分自身もトラウマがみえると、最初は逃げたいって思う。でもセラピーを続けると、これは一生自分の体験として消えないんだってことに気づく。そこにいった時に初めて、癒しがあるんですよ。
人間はなかなかそこにいけない。COVID-19もそうだしグラウンドゼロもそうだし。コロナ渦が終わっても、ノーマルな世界に戻ることはない。
ーノーマルに戻るのではなくて。
フジムラ:でも、それがサバイバー。みんなサバイバーなんです。それを認識することが大切。ノーマルに戻ることはできない。僕たちがこのコロナ禍で体験したこと、苦しみが、その傷として残るんだって、それがわかった時に癒しがくる。でも癒しがくるときに、過去の傷をどういう風に新しくしていくんだ?という問いが生まれる。
そのトラウマがアイデンティティーに固定化されてしまうと、成長しない。だからこれからカイノス、新しい新しさだとか金継ぎ的な発想だとかが必要だと思ってます。
ー熱を加えると姿を変える膠は、まさにカイノスですね。そうした考え方と日本画という技法がマッチしたのでしょうか。
フジムラ:マッチした。ただ、それを最初は感性でしか捉えてなかった。面白いなって思って。齋藤先生も「フジムラくんは学ぶのが早い」と言ってくれて。日本画が僕の肌にあってたから、普通は学部で2年間かかってやっとマスターするようなことを、僕は1ヶ月でできちゃった。だから鎌倉での経験っていうのは大きいと思っています。

緑青の岩絵具を乳鉢で砕いた様子
幼少期時代の鎌倉を経て、日本画的な美を肌で体感していたフジムラ氏。
出自の運命的なエピソードと、そこから生まれる日本美術の素材とキリスト教にまつわる美学のクロスオーバーは、日本で過ごしていた筆者にとっても非常に刺激的な内容でした。
後編では同氏の作品と素材について迫ります。