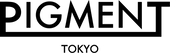インミンブルー(YInMn Blue)とは、オレゴン州立大学のサイエンスチームが電気系の利用のため新しい原料の研究をしていた際、偶然発見された人工的な青色系顔料です。
この顔料は他の構造体が混ざった酸化マンガンを高温で構造をテストした際に生まれました。 PIGMENT TOKYOでは2018年よりインミンブルーのチューブ入りアクリル絵具と顔料、そして日本国内専売品として、同顔料を使用した油絵具の販売をしております。
(*インミンブルーの油絵具は販売を終了いたしました。)
今回、当ラボでは古典的な画法を用いながらも同時代性を探求する画家、諏訪敦氏にインミンブルーの素材提供を行いました。 近年では『諏訪敦 絵画作品集 Blue』(2017年、青幻舎)という作品集も刊行した、諏訪氏。果たして氏は、この「全く新しい青」をどのように感じ、触れたのでしょうか。 また氏の作品は、どのような材料学的な知見を元に制作されているのでしょうか。その背景に迫ります。
—アーティスト活動の中で明確に「素材」を意識されたのはいつ頃からでしょうか。
諏訪敦氏(以下諏訪/敬称略):武蔵野美術大学の油絵学科には、主に古典技法の研究と応用の実践をする絵画組成室があります。学部生には必修でテンペラ絵具の用法や油彩との混合技法を経験する機会があります。素朴で味わい深い絵肌とエッジの効いた描写が可能なテンペラにはまって、大学院のころから自主制作の中で多用していました。しかし「混合技法」という名称は、当時から複数の意味を持つ混乱含みの言葉でした。またそれを施した作品も高湿度な日本の風土では管理が難しく、次第に制作に使うことが減っていきました。しかし絵画を物質的側面から理解する重要な経験だったと思います。
大学院修了後、1995年に文化庁芸術家派遣在外研修員として、スペインに2年間留学しました。その時にプラド美術館に通い詰め、アルブレヒト・デューラーの模写などを行いました。ヨーロッパのアカデミーにおいて、模写は絵画技術習得の手段として伝統的に認められています。プラドには画学生だけではなく模写を描くことを収入源にしている画家もいて、多くの名画の前には彼らのためのイーゼルが立っていました。どうあれプラドの絵画作品は国民に開かれており、彼らを管理する部門まで存在することに文化の厚みを感じたものです。
しかしながら技法や画材の重要性というのは認めながらも、そこにマニアックに拘泥することに違和感も感じはじめたのもこの頃です。絵具の操作感覚や描画する身体性の重要度がより気になってきたということでしょう。
—インミンブルーを触ってみて、最初はどのように感じましたか。
諏訪:「完璧な青」と聞いていたので、どのくらい青いのだろうって、個人的に期待度が非常に高かったのです。緑と赤の光を吸収して、結果的に青のみが鮮明に現れるという触れ込みでしたよね。より青い色、青いと感じる感覚の底というか限界をみたいという気持ちが強くて、つまり自分達はどこまで「青」を知覚できるのかに興味がありました。心もち暗いという印象で少し赤みを感じられたのは意外なことでした。とはいえ、こうして普及する前夜の状況にある貴重な顔料を前にすると、少年のように高揚してしまいますね。

机に並べられたインミンブルーの顔料、アクリル絵具(DERIVAN)、チューブ絵具(ホルベイン)
—絵を描くことが好きな人は、そのような価値観がありますよね。
諏訪:そこから絶対に逃れることはできません。例えば貴重な鉱物を使った顔料を見ると誰もがぐっとくるでしょう。天然由来の顔料は不純物が多く、微妙な差異も含めて楽しめます。また、品質とは直接関係のないエピソードが価値を付加させてしまうこともあります。 ただ、この質素なスタジオをご覧になれば分かるように、自分の代で使いきれないような高価な岩絵具の類を、ずらっと並べるような趣味はありません。私は安価な画材や専門画材以外の塗料などにも、用途はあると考える方なのです。
 無機質で緊張感のあるスタジオには、いくつかの小さなモチーフが置かれていた。
無機質で緊張感のあるスタジオには、いくつかの小さなモチーフが置かれていた。
—使われた感想はいかがでしたか。
諏訪:最初は「どんな人がこの色を必要とするんだろう」と考え込んでしまいました。というのも、近似した色味を作れる合成ウルトラマリン・ブルーの方が誰にだって使いやすいはずで、この高価な顔料をあえて選び、人間には検証できないような長い時間を経て、うたわれている耐候性の高さを確認できるわけでもないわけですし。 ただ、イヴ・クラインの「インターナショナル・ブルー(IKB)」に似た感触がある。イヴ・クラインが生きていたら、インミンブルーを選んだかもしれませんね。
—IKBは少しマットというか落ち着いた、奥にいくような質感がありますよね。
諏訪:粉体の顔料を使い乾性油で溶いて使ってみたら、暗くてもはっきり青く、光を吸収しているような冷たさを感じる感触が得られて、かなりぐっときました。 これは次の展覧会のメインビジュアルの作品のうちのひとつですが、どこにインミンブルーを使っているかわかりますか。青色顔料は3種類使っているのですが、判別しやすいと思います。

《Mimesis》諏訪敦、2022年 サイズ(cm)259×162 パネル、キャンバス、油絵具
この写真でいうと、スカート左側の青い帯状の部分は天然ウルトラマリンとインミンブルーのコンビネーションでグラデーションを作っています。はっきりと特性がわかるのは、左側の背景に溶け込む腕の青い斑と、スカート中央の白い絵の具の流れている隙間に見える、深海のように暗く深い青色です。インミンブルーを単独で使用したのはそこです。
—そうですね。チューブ絵具に適した粘度のものを、商品に採用しております。
諏訪:はい、ただ顔料を自分の好みの固さに乾性油で溶くと、さっきのクラインブルー(IKB)じゃないけど、吸い込まれるような触感を実現できました。これはちょっとすごい。インミンブルーの特別さは、こんなに暗くてもきっちりと青く描けることです。窪んだ感じの錯視も演出できそうです。光が吸い込まれていて別空間のよう。例えば黒色顔料……アイボリーブラックなどではこのようにワンストロークでは隠蔽できない。びしっとせずに、どこかホンワカしちゃうんです。なぜこのような異次元な色が必要だったかというと、この絵が即物的な意味でのリアリズム絵画とはちょっと違っているからです。
—どのような状態でしょうか。
諏訪:深夜にラジオのチューニングを探っていると、異国の暗号なのでしょうか(笑)、ノイズやら聴きなれない言語で混線した状況になることがあります。あれ、不思議な気分になりますよね。世界でたった独りになったような浮遊感がある。それを絵に置き換えてみたかった。そこで目にする色彩は人間的な感情から乖離しているというか。
 2枚の作品を制作する場合、このくらいのブルーグレーの色幅を作るという諏訪氏。
2枚の作品を制作する場合、このくらいのブルーグレーの色幅を作るという諏訪氏。
—それでこのような作品を描かれたのですね。
諏訪:私は1999年から、大野一雄さんという舞踏家を描き続けていました。彼は2010年に104才で亡くなっているのですが、写実絵画の一般的な定義だと描けないこということになりますよね。対象を二度と実見できないわけですから。
だけど私の場合は、描き続ける意思がある限り、人間も召喚できるというか、関係性を延長できるはずだと考えていて、そのためにさまざまな手を尽くします。先ほどお話しした《Mimesis》の場合は不在のダンサーのイメージを手渡していくときに、一つの絵画空間の中に二つの時間軸が混線しているように描いています。自然の再現とはいえない描写には、異次元のように吸い込まれる深さを表現できる青が必要でした。
—どのようなプロセスで制作を進められたのですか。
諏訪:《Mimesis》は大野一雄さんとの関係を継いでいくために描いたのですが、川口隆夫さんというパフォーマーとの協働で制作しています。彼は2021年度芸術選奨文部科学大臣賞を受けていますが、その前には大野一雄さんの完全なコピーをする「大野一雄について」というチャレンジングな舞台を敢行し話題になりました。私の要求には彼のような存在は願ってもないものでした。《Mimesis》というのは模倣を意味しますが、ギリシアの古代哲学では創作芸術の根幹を示すものとして語られています。私のような写しに、描くことを表現言語とした制作の本質を問い直す企みもありました。
—諏訪さんは、素材とモチーフに関係性を持たせることが多いですか。
諏訪:それは私にはあてはまりません。私は本来受動的だからです。大野一雄さんの場合は自分から絵を描かせてくださいと申し出たのですが、これは例外的ですね。ほとんどの場合、描いてくれと依頼してくださる人たちを取材対象にしています。 今回は、PIGMENT TOKYOからインミンブルーについての話をいただいたので、自分のストーリーを広げて接続してみたという感じです。いつのまにか「青」が制作にまつわるイメージとして私に貼りついているとは知らなかったし、画材との能動的とはいえない出会いにも、後から意味を与えていくというか。

《Solaris》諏訪敦、2017-21年 サイズ(cm)91×60.7 白亜地パネル、油絵具
—人工的な青ならではの魅力、というのもありますね。
諏訪:例えばこれは歌川國芳の《源氏雲浮世絵合 玉葛》ですが、皆さんをお招きするために私物を壁に飾っておいたのには理由があります。この作品には江戸時代の日本人にビジュアル・ショックをもたらしたベロ藍(ベルリン藍/プルシャンブルー)が使われているからです。
ベロ藍は18世紀に輸入されて以来、浮世絵を変えました。それまで日本で「青」といえば蓼藍(たであい)を発酵させた本藍や、露草の花から抽出した淡い染料などでした。それでも透明感のある青が表現できましたが、色味が弱く扱いにくかったといいます。一方、ヨーロッパで流行していたベロ藍はオランダ経由で日本に入ってきて、浮世絵の顔料として盛んに使われるようになりました。この異国の青色が1704年に発明されてから140年ほどが経過し、十分に知れ渡った時代に本作は刷られたことになります。

諏訪氏の個人研究室にかけられている《源氏雲浮世画合 玉葛》。 歌川 國芳による1846年の作品です。
—西洋の場合は少し違いますよね。
諏訪:17世紀のオランダ付近ではラピスラズリの逸話はよく知られていますよね。黄金に匹敵する青色顔料の高価さは、発注にお金がかかっている証。市民層にも広がった絵画市場の中で、その価値を担保することにもなっていたのでしょう。 一方で人工顔料のベロ藍という色は、それまで草木染めのように淡い色調べに親しんでいた18世紀の日本人の色彩感覚と、かけ離れたものだったのではないでしょうか。強力に染まりすぎるというか。ベロ藍を多用したといわれる葛飾北斎による《冨嶽三十六景》でも、本藍との併用などの工夫がみられますし、この歌川國芳作品にも正確な処方はわかりませんが多様で豊かな青を確認できますよね。 インミンブルーも今より価格が安くなり普及したら、いろいろなアーティストによって最適な使用方法が見出されていくのでしょう。
作品にもたびたび青色が登場する諏訪氏。どこかクールでありながらも、確かな美学を持ち素材に向けられる眼差しは、緻密なプロセスを経て制作される絵画作品にも通底するものがあるように感じました。
2022年12月から府中市美術館(東京都)で開催される諏訪敦氏の個展、『眼窩裏の火事』では今回のインタビューで登場した、インミンブルーを使用した作品も展示されます。 世界最新のアーティフィシャルな青色の魅力を、ぜひ会場で体験してみてください。
・プロフィール

2020年11月16日 大野一雄舞踏研究所にて川口隆夫を描く諏訪敦氏 撮影:野村佐紀子
諏訪敦 すわ・あつし 画家。
1967年北海道生まれ。1994年に文化庁派遣芸術家在外研修員としてマドリードに在住。帰国後、舞踏家の大野一雄と大野慶人親子を描きシリーズ作品を制作。これを契機に絵画の原点回帰としての写実表現から、取材プロセスに比重を強めたスタイルへの展開を見せている。
成山画廊、Kwai Fung Hin Art Gallery など内外で発表を続け、2011年、NHK 『日曜美術館 記憶に辿りつく絵画~亡き人を描く画家~』 での単独特集、2016年には、ETV特集 『忘れられた人々の肖像“画家 諏訪敦 満州難民を描く”』 が放送され、その制作の徹底性が広く知られる事となった。
2018年 武蔵野美術大学造形学部油絵学科教授に就任。
公式図録「諏訪敦『眼窩裏の火事』」(美術出版社) を、2022年12月に刊行。
Twitter : @suwakeitai
Instagram.com : suwa_atsushi_artist
・展覧会情報 諏訪敦『眼窩裏の火事』 SUWA Atsushi Fire in the Medial Orbito-Frontal Cortex
(こちらの展示は終了しております。)
2022年12月17日(土) ~ 2023年2月26日(日)
*休館日:月曜日(1/9は開館)、12/29(木)~1/3(火)、1/10(火) *開館時間:午前10時~午後5時(展示室入場は午後4時30分まで)
観覧料:一般700円(560円)、高大生350円(280)円、小中生150(120)円 *( )内は20名以上の団体料金。
*未就学児および障害者手帳等をお持ちの方は無料。
*府中市内の小中学生は「府中っ子学びのパスポート」提示で無料。
*企画展観覧料金で常設展もご覧いただけます。
主催:府中市美術館
特別協力:成山画廊
協力: NPO法人ダンスアーカイヴ構想 東屋