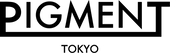更新日:2024年10月31日
私たちの国で古くから親しまれてきた雲母(うんも)。光をキラキラと反射させることから、古くは「きら」及び「きらら」と称されていました。
胡粉のように真っ白ではなく半透明な色のため、白の絵具としてではなく他の顔料と混ぜたり、エフェクト顔料のように基底材に薄く塗って煌めきを出す用途で使われています。
それ以外にも効果は多岐に及び、電気絶縁や耐熱材料、古代では漢方薬や防虫材としても使われていたそうです。

こちらが雲母の原石の写真です。
雲母を美術作品に用いたのは、日本だけではありません。日本美術で用いられた雲母とは少々異なりますが、ヨーロッパ大陸では加工が非常に容易なことから、セレーナ石(雲母片岩)という名前の建材として親しまれていました。
例えばフィッツィ美術館に収蔵されている「マニフィカートの聖母」という円形絵画(トンド)には、同石で造られた窓枠が描かれており、そこから14世紀のフィレンツェの建築様式がうかがえます。
閑話休題、話を日本美術に戻しましょう。
かの有名な東洲斎写楽による「三世大谷鬼次の奴江戸兵衛」も、雲母刷りの技法が用いられておりました。ここ数年で、再ブームが訪れているトレーディングカードにもキラキラとした印刷が施されているのと同じように、かつての江戸の人々も角度を変えると輝く煌めきに魅せられていたのでしょう。

《Kabuki Actor Ōtani Oniji III as Yakko Edobei》Tōshūsai Sharaku,1794,The Metropolitan Museum of Art
そのほかにも、雪の煌めきを表す為のエフェクト表現として、雲母が用いられておりました。例えば「雪景山水図」では、水墨画の代表的なモチーフである霞がかった広大な峰々が、墨と雲母のコントラストで巧みに描かれております。

《Snowy Landscape》Toki Tōbun,ca. 1550,The Metropolitan Museum of Art
そのような雲母ですが、絵具になる前はどのような形状をしているかご存じでしょうか。
当ラボでは粒子の大きさが異なった3種類の雲母をご用意しております。この素材は薄く平行にはがれやすい性質を持っているため、円形というよりは小さなプレート状の形をしています。

前述の通り、この顔料だけでは隠ぺい力と着色力を有していないため、単体では塗っても大きな変化はございません。
しかし、他の絵具と混ぜることで効果を発揮します。
今回は荒目、中目、細目の3種類を、メディウムを変えて練り合わせてみました。

【使用画材】
上段:アクリル絵具カドミウムイエローオレンジ(松田油絵具)/ 雲母 荒目(ナカガワ胡粉絵具)
中段:キナクリドンバイオレット(ホルベイン画材)/ 雲母 中目(ナカガワ胡粉絵具)
デュオ クイックドライングリキッド ※こちらの商品は販売を終了いたしました。
下段:水干 若葉(ナカガワ胡粉絵具)/ 雲母 細目(ナカガワ胡粉絵具)
ガムアラビック 水彩メディウム(クサカベ)
基底材:竹和紙 水彩画用(アワガミファクトリー)
アクリル絵具、デュオメディウム、アラビアゴムと、性質の異なるメディウムを雲母と混ぜてみました。マチエールの差異はあるものの、糊材を変えても荒目、中目、細目の特徴が出ることがわかりました。では、上段から観察していきましょう。
荒目の雲母は、画面に光沢を付与する効果以上に、絵肌にザラつきを与えるために使用されます。サンドマチエール用メディウムを混ぜた時のような、均一でアーティフィシャルな質感というよりは、剥落した絵具のようなツブ感を残しつつ、味のあるキラキラした画面を作り出すことができます。
中目は荒目より光沢感が強く出ています。これは塗面に光沢感を与えるために最もベストな粒子径になるように作られているからです。雲母の輝きを楽しみたいという方は、まず雲母の中目を買うと良いでしょう。
細目は絵具と混ぜ合わせることで不透明度が上がり、少しマットな質感になります。しかし、光源や角度を変えて見るとかすかに光る不思議な質感が魅力的です。写真では写りにくいこの絵肌。ぜひご自身でお試しください。
それ以外にも、糊材を塗った上からこの顔料を散らすことで、砂子のようなザラつきのある質感を生み出すことができます。接着剤としてマットメディウムを薄く塗った上から手で雲母をふりかけました。また砂子筒を用いることで全体に満遍なく散らすことが可能です。
砂子筒にも網目の荒いものから金泥用の細かいものまで、合計6段階の商品をご用意しております。使用する雲母の粒径によって必要な目の細かさも変わってきます。
当ラボで販売している雲母を使用する場合は、荒目・中目・細目がおすすめです。

「雲母」という言葉から、日本画材として思われがちなこの顔料ですが、実はさまざまな表現の可能性が秘められています。塗った画面を傾けながらキラキラ感を楽しむというのも良いでしょう。
ぜひ、あなただけの雲母の使い方を見つけてください。
参考資料
グローリア・フォッシ『ウフィッツィ美術館 芸術 歴史 コレクション』松本春海 訳 (GUNTI.2006年)
吉岡幸雄、福田伝士 『日本の色辞典』(紫紅社.2000年)